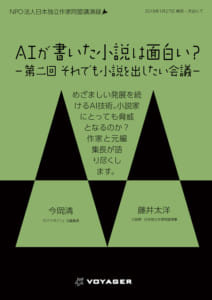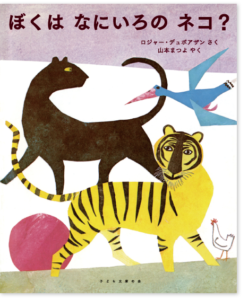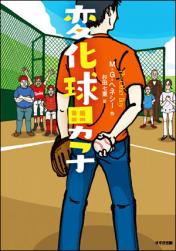12/10日号で配信された「書評のメルマガ」では『変化球男子』『明日のランチはきみと』『サイド・トラック 走るのニガテなぼくのランニング日記』『シロクマが空からやってきた』『クリスマスのおかいもの』 『ゴッホの星空 フィンセントはねむれない』『ねむりどり』『シルクロードのあかい空』をご紹介しました。
http://back.shohyoumaga.net/
———————————————————————–
■「いろんなひとに届けたい こどもの本」/林さかな
———————————————————————-
90 豊かで複雑な雑多な世界
いよいよ今年最後のメルマガ記事になります。
みなさんにとって2018年はどんな一年だったでしょうか。
もう来月は新しい年!
今年をしめくくる本としてどれを紹介しようかと読んでいたら、どれもこれ
もアタリばかりでうれしくなったので、できる限りご紹介します!
トップバッターはこちら。
『変化球男子』
M・G・ヘネシー 作 杉田七重 訳 すずき出版
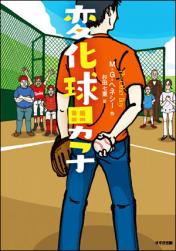
おもしろいタイトルに惹かれて読み始めたら、ものすごい吸引力!
ロサンゼルスの中学校に通う男子、シェーンが主人公。野球部で活躍し、ジョシュという大親友もいて、学校生活をエンジョイしています。
思春期まっただなかのシェーンには悩みもあり、それはなかなか人にはいえないもので、親友にも秘密にしています。
さて、その秘密とは――。
シェーンの悩みとは、女の子の身体なのに、心は男の子ということ。離婚している両親のうち一緒に暮らしている母親は理解しているのですが、父親は手術を受けて身体も男の子になりたいシェーンの気持ちをまるごと受け入れるこ
とができません。悩みを軸に、家族、親との関係、友情などたくさんのことが語られていて、シェーンの悩みはどう着地するのか。このテーマ、悩んでいる日本の子どもたちにも届いてほしい本です。
『明日のランチはきみと』
サラ・ウィークス/ギーター・ヴァラダラージャン 作
久保陽子訳 フレーベル館


アメリカ人作家、サラ・ウィークスと、インド人でアメリカ在住の小学校教師、ギーター・ヴァラダラージャンの2人で執筆した作品です。
主人公のラビはインドからアメリカに引っ越してきた小学5年生。インドでは優秀だったので、アメリカでも勉強に遅れをとることはないと思っていたのですが、インド式計算もクラスの先生には受け入れてもらえず、いままで優等
生のスタンスでいたがゆえに、落ちこぼれのレッテルを貼られてしまうギャップに苦しみます。
もう一人の主人公はジョー。「聴覚情報処理障害」という聴く能力に問題があり、自分に自信がもてず学校では消極的です。
物語はこの2人のシチュエーションが交互に語られます。お互いのバックグラウンドはかなり違うのですが、少しずつ打ち解けていき、一週間も過ぎると2人はぐっと近しくなっていきます。
文化の違う国に転校するハードルの高さ、それを超える大変さがユーモアも交えて書かれていて読後感が爽やかです。
『サイド・トラック
走るのニガテなぼくのランニング日記』
ダイアナ・ハーモン・アシャー作 武富博子訳 評論社


主人公の少年フリードマンは「注意欠陥障害」を抱えています。運動音痴にも関わらず、新しくできた陸上部に入り、クロスカントリー競走に挑戦することに。
スポーツ物語とくれば、中心にすえられるのは、スポーツ得意な人物が多いですが、今回はそうではありません。サブタイトルにあるように、走るのニガテなぼくのランニング日記なのです。
登場する人物で魅力的なのは、フリードマンを支えるのは79歳のおじいちゃん。高齢者住宅〈ひだまりの里〉にいたのだが、ある事がきっかけでフリードマンの家で同居することになるのです。フリードマンのよき理解者であるおじ
いちゃんは、クロスカントリーに挑むことを誰よりも応援します。
そしてもう一人、転校生の女子ヘザーも、フリードマンのよき友だちになり、2人の友情も物語の柱です。
最初は望まなかったクロスカントリー走、フリードマンはどんな風に走るのか、本書でぜひみてください。
『シロクマが空からやってきた』
マリア・ファラー 作 ダニエル・リエリー 絵 杉本詠美 訳
あかね書房


シロクマシリーズ第二弾。とはいえ、前巻を読んでいなくても気にしなくて大丈夫です。
主人公ルビーの母親は、父親と離婚して以来、仕事も手につかず、幼い弟の世話もルビーに任せることが多くなっていました。ルビーは必死で母と弟を支えますが、そうはいってもまだ子どもなのです。
そんなルビーの前に、シロクマがあらわれます。たくさん食べる(つまり、食費もかかる)体の大きなシロクマを住んでいるマンションョンに連れていくわけにはいきません。けれど、なりゆきでマンションの下の階に住んでいるモ
レスビーさんの助けもあり、シロクマとの生活がはじまります。
言葉は発しないシロクマですが存在感と行動力はあります。ルビーも次第にシロクマと打ち解けていき、母親の問題も解決に向かっていきます。
ものいわず寄り添ってくれる(静かにではないですが)シロクマの存在感が伝わってきて、ルビーの心がほぐれていくのにほっとします。親が病気になった時、子どもは大人の役目も担わされることがあります。そんな子どもたちの
ことはヤングケアラー(若い介護者)と呼ばれ、日本にも少なくない子どもたちが同じ立場にいます。
物語のあったかさと子どもの問題をやんわりしっかり伝えてくれる好著です。
さて、12月といえばクリスマス!
贈り物におすすめの絵本、
ストレートにクリスマスを楽しめる絵本をご紹介します。
まずはこちらから。
『クリスマスのおかいもの』
ルー・ピーコック ぶん ヘレン・スティーヴンズ え こみや ゆう やく
ほるぷ出版


ペン画に水性の色をのせた、あたたかい雰囲気のクリスマス絵本。
男の子のノアはママと赤ちゃんの妹メイの3人でクリスマスプレゼントの買い出しに出かけます。
ママは小さい子ども2人と一緒なので、ノアたちに目をくばりながら、プレゼントの買い物に集中していきます。ノアは大事なオリバー(ゾウのぬいぐるみ)と一緒にメイと遊んで待っています。
買い物が終わり、一息ついたとき、ノアは気づくのです。オリバーがいない! 大変! 買い物の次はオリバー探し……。
オリバーの存在の大事さをママがしっかり受けとめているからこそのラスト。
クリスマスの幸福感に満ちています。
贈り物絵本でおすすめはこちらの3冊。
『ゴッホの星空 フィンセントはねむれない』
バーブ・ローゼンストック 文 メアリー・グランプレ え
なかがわちひろ 訳 ほるぷ出版


この絵本では、画家になるまえのゴッホが描かれます。子どもの頃から、夜中に何度も目を覚ましていたこと、夜でも嵐でもひとりで散歩に出かけていたことを、私はこの絵本で初めて知りました。
その時に感じた心持ちが後に夜空を描くときに塗り込められたのでしょうか。
ゴッホの絵といえば、ひまわりもすぐ思いつきますが、夜空の絵も強い印象を残します。我が家の高校生の娘っこにゴッホの絵で何がすぐ思いつく?と聞いたところ、星空が独特だよね、とこたえてくれました。
夜なかなか眠れなかったゴッホが、画家になり、「色彩をつかって夜の闇をえがくこと」を自身の課題とし、独特な夜空を描いていく過程を本書でじっくり楽しめます。
『ねむりどり』
イザベル・シムレール 作 河野万里子 訳 フレーベル館


『シルクロードのあかい空』
イザベル・シムレール 文・絵 石津ちひろ訳 岩波書店


シムレールの絵本は、とにかく強いインプレッションを読み手に与えてくれます。
ひっかいたような細い線で幾重にも色を重ね、その繊細さの重なりがハッとさせる美しさにつながっているのがシムレールの絵。
『ねむりどり』では羽毛のふわふわさが、紙の上からもリアルに感じられ、ついつい手がのびて紙の上からなでてしまいます。
『シルクロードのあかい空』では山裾にしずむまっかな夕陽の明るさとともに、強い目力をもつ子どもも印象に残ります。
贈り物にもぴったりですし、
直接手にとって時間をかけてみて欲しい絵本です。