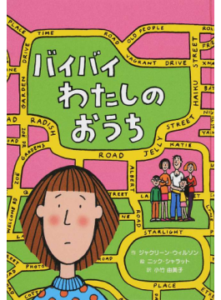1/10日号で配信された「書評のメルマガ」ではユーモアたっぷりの本について書きました。
http://back.shohyoumaga.net/?eid=979078
———————————————————————-
■「いろんなひとに届けたい こどもの本」/林さかな
———————————————————————-
79 共に生活する楽しみ
2018年が始まりました。
年末年始のハレの日が過ぎ、日常が戻っているころでしょうか。
さて今年最初にご紹介するのはシリーズ2作。
『モルモット オルガの物語』
『オルガとボリスとなかまたち』
マイケル・ボンド 作 おおつかのりこ 訳 いたやさとし 絵 PHP研究所




作者は「くまのパディントン」シリーズを書かれたマイケル・ボンドさん。
さみしいことに昨年亡くなられ、日本語に訳された本はみていただくことは叶わなかったそうです。
本書は娘のカレンさんが飼っていたモルモットをモデルに、空想力ゆたかなオルガが愉快に動き回る物語。
表紙のモルモットたちの愛らしさにまず惹かれ、
一巻目の冒頭からこれはおもしろそうだとわかりました。
――オルガ・ダ・ポルがはまちがいなく、とくべつなモルモットです。
とくべつなモルモットの話!
オルガは自分の名前を飼い主のカレンにどのように伝えたか。
ネコのノエルとはどのようにわかりあったか。
空想が紡ぐめくるめくお話。
などなど
オルガの躍動感が読み手に伝わってきて、ワクワクというか、次は何をするのかなという楽しみが読んでいる間中続きます。
おおつかさんの翻訳は言葉がやわらかく、詩的で、物語にとてもあっています。オルガやまわりの友だちの言葉は時に深淵で哲学的でもあり、大人が読んでも、はっとします。
私の好きな言葉は、ハリネズミのファンジオによるもの。
ファンジオはオルガに自分な好きな場所“天国が原”の話をし、オルガもその場所に行きたくなります。なんとか、囲いから抜け出し、ファンジオと出かけます。しかし、“天国が原”はオルガにとってはよくわからない場所でした。
そんなオルガにファンジオはこういいます。
「美は、みるものの目にやどる。おいらのまどからは、すてきな場所にしかみえないけどな」
うんうん、ファンジオのいうこと、よくわかります。
小学校低学年から楽しめる物語。
周りのお子さんにすすめてみてください。
動物好きだとなお喜ばれるでしょう。
訳者おおつかさんによる、オルガのブログもぜひ。
作中に出てくる料理、その名も”あなのなかのヒキガエル”もブログで紹介され、つくりたくなりました。
「もっと もっと モルモット オルガ」
https://olga-da-polga.muragon.com/
もう一冊はうれしい復刊児童書
『バイバイわたしのおうち』
ジャクリーン・ウィルソン 作 ニック・シャラット 絵 小竹由美子 訳
童話館出版
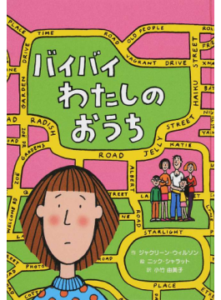
本書は2000年に偕成社より刊行されていたものの復刊。翻訳は全面的に見直されています。
刊行された当時読んでいたので、久しぶりの再読です。
ジャクリーン・ウィルソンさんの作品は1995年に翻訳家の小竹さんが訳された『みそっかすなんていわせない』(偕成社)を皮切りに、日本でもファンが広がりました。イギリスで大人気の作家、ジャクリーン・ウィルソンは複雑な家庭環境下の子どもの気持ちをよくすいとっていて、なんでわかるの?と聞きたくなるほどリアルです。
私自身、中学のときに両親の離婚を経験していますが、まわりの友だちには相談できず本にずいぶん救われました。
ひこ・田中さんの『お引越』や今江祥智さんの『優しさごっこ』がそうでしたが、ウィルソンさんの本を初めて読んだときは、もっと早く読みたかった!とくやしく思ったほどです。
さて、この物語のいちばんの魅力は語り口が湿っぽくないところです。
親の離婚は子どもにとっては不幸なことが多いですが、だからって暗く重たく書く必要はなく、からりと悲しさやしんどさを語ってほしいのです。
『バイバイわたしのおうち』はパパとママとアンディーの3人で桑の木のある一軒家で暮らしていたのが、両親の離婚によって、1週間事に双方の家を行ったり来たりする暮らしを強いられるようになった物語。
両親の仲が破綻していても、子どもとの関係は破綻していないのだから、アンディーにとっては、どうにかやり直せないか、また一人っ子に戻りたいと願うのはとっても理解できます。
双方ともに異母兄弟がいて、落ち着く場所がなく、ストレスをため続けるアンディー。そんなアンディーの親友はシルバニア・ファミリーのうさぎ人形、ラディッシュ。
ラディッシュのおかげで、アンディーはもう一つの居場所も得ることができるので、そのあたりはぜひ本を手にとって読んでみてください。
子どもの選択肢は少ないゆえに、逃げ場がなかなか見つからない。家、学校以外の居場所は大事です。
アンディーにラディッシュがいてよかった。
ニック・シャラットのイラストも物語にぴったり。子どもも大人も表情がいい、仕草がいい。みんな憎めない人物に描いています。
ウィルソンさんの物語を必要とする子どもたちにこの本が届きますように。
大人も読んで広めましょう!
それでは、今年もよろしくお願いいたします。